
価格や機能など見るべき指標を解説
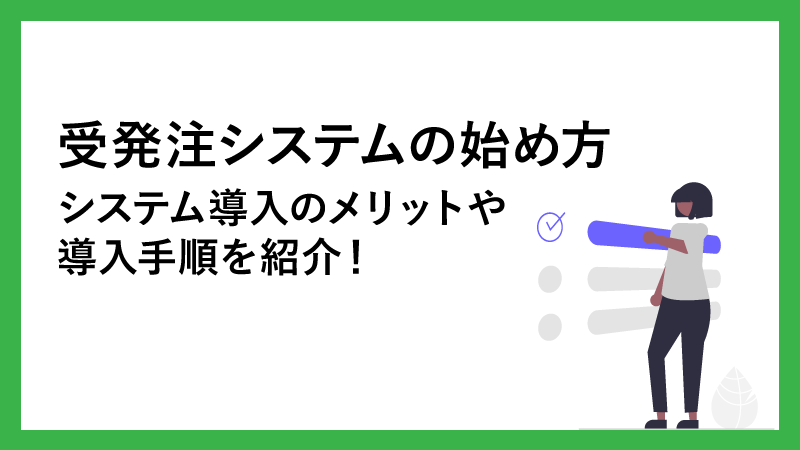
皆さんは企業間の受発注業務をどのように管理していますか?電話やFAX、紙などアナログな方法で受注・発注を続けている企業も少なくありません。しかし、アナログ管理では業務効率化や人的ミスの削減、コスト削減が難しく、ヒューマンエラーや管理コストの増加が課題となります。
そこで登場するのが受発注システム。受発注業務のデジタル化・効率化・情報の一元管理が実現します。この記事では、受発注システムの概要やメリット、導入手順、種類、注意点や選び方までわかりやすく解説します。
受発注システムは、企業間の受注・発注業務をデジタル化し、一元管理できるシステムです。従来の電話やFAX、紙、メールでのやり取りを効率化し、クラウド型サービスの導入も進んでいます。発注書作成や在庫管理、納期管理、請求書発行などをオンラインで完結でき、リアルタイムで状況把握が可能です。これにより、業務効率化やコスト削減、ヒューマンエラーの防止、データ分析による戦略的な経営が実現できます。用途に応じて「受注管理システム」や「発注管理システム」と使い分けることも大切です。
受発注システムを導入すると、業務効率化やコスト削減、ヒューマンエラー防止など多くのメリットがあります。
受注から発注、在庫管理、請求書発行までの業務を自動化・一元管理でき、手作業の負担を減らし、迅速な対応が可能です。書類作成や保管のコストも削減でき、ペーパーレス化が進みます。記載漏れや入力ミスも防げるため、業務の正確性や信頼性が向上します。さらに、取引データをリアルタイムで管理・分析できるため、戦略的な経営判断や販売計画にも活用できます。
リモートワークや24時間対応にも対応でき、顧客サービスの向上にも役立ちます。
皆さんは企業間の受発注業務をどのように管理していますか?電話やFAX、紙などアナログな方法で受注・発注を続けている企業も少なくありません。しかし、アナログ管理では業務効率化や人的ミスの削減、コスト削減が難しく、ヒューマンエラーや管理コストの増加が課題となります。
そこで登場するのが受発注システム。受発注業務のデジタル化・効率化・情報の一元管理が実現します。この記事では、受発注システムの概要やメリット、導入手順、種類、注意点や選び方までわかりやすく解説します。
受発注システムとは、企業間で行われる商品の受注・発注業務をデジタル化し、一元管理できるシステムです。従来の電話・FAX・紙・メールによるやり取りをシステム上で効率的に管理できるため、「受発注管理システム」や「Web受発注システム」とも呼ばれ、近年クラウド型SaaSの導入も進んでいます。
このシステムを導入することで、発注書作成や受注内容の確認、在庫管理、出荷指示、納期管理、請求書発行など、一連の受発注プロセスをオンラインで完結できます。リアルタイムで商品やお金の流れを把握できるため、業務の透明性が高まり、人的ミスやヒューマンエラーの削減、業務効率化、コスト削減が実現します。また、過去の取引データも簡単に蓄積・分析でき、戦略的な在庫管理や発注計画の立案にも活用できます。
受発注システムの導入は、業務の効率化や顧客満足度の向上、企業の競争力強化に大きく貢献する重要なツールです。用途や業務内容に応じて、「受注管理システム」や「発注管理システム」と使い分けることもポイントです。
受発注システムは、受注から発注、請求・在庫・支払い管理までの一連の業務をデジタル化するシステムで、主な機能例は以下の通りです。
情報の一元管理によって、取引履歴や在庫状況をいつでも正確に把握できるのが大きな特長です。
受発注システムには主にクラウド型とオンプレミス型の2種類の導入形態があります。
「クラウド型」受発注システムはインターネット経由で利用するため、初期費用が抑えられ、保守・運用も不要。環境構築が不要のため導入してすぐ利用できる場合が多いです。
一方、「オンプレミス型」受発注システムは自社サーバーや自社ネットワーク環境を構築するため、導入・運用コストが高いですが、カスタマイズ性やセキュリティ面に優れます。
自社の業務規模やセキュリティ要件、ITリソースなどを考慮して最適な形態を選ぶことが重要です。
受発注システムには、Web受発注システムとEDI(電子データ交換)の2つが代表的です。
Web受発注システムはブラウザで操作でき、直感的なUIが特徴。
EDIは標準化されたデータフォーマットで企業間の大量取引を自動化できるため、大手企業やサプライチェーン全体での効率化に最適です。
自社の取引先や業界事情に合った種類を選ぶこともポイントです。

受注発注システムを導入することで、企業の業務効率化やコスト削減、ヒューマンエラー防止、戦略的な経営判断など、さまざまなメリットを得ることができます。ここでは主なメリットを詳しく解説します。
受注から発注、在庫管理、請求書発行まで一連の業務フローをシステム上で自動化・一元管理できます。
これにより、従来の電話・FAX・紙・メールによる手作業が不要となり、注文データの入力や承認、納期調整などもスムーズに行えるため、担当者の業務負担が大幅に軽減されます。
リードタイムの短縮や迅速な対応も実現し、顧客満足度向上につながります。
受注発注システムの導入により、紙の書類作成・印刷・郵送・FAXなどにかかるコストを削減できます。
データ管理もクラウド上で完結するため、ファイリングや書類保管に必要なスペース・コストも不要となり、ペーパーレス化による経費削減が可能です。
工数削減による人件費の抑制も期待できます。
システム上で受注内容の記載漏れや入力ミスを自動チェックできるため、紙やFAXによる誤記入・転記ミス・確認作業の負担が減少します。
エラーの削減は再申請や修正対応の手間も省き、取引先との信頼性向上や業務スピードのアップにも貢献します。
受注・発注・在庫・請求などの情報をリアルタイムで一元管理できるため、複数拠点や部署間でのデータ共有も容易です。
蓄積された取引データを分析することで、売上推移や購買傾向の把握、在庫管理の最適化、戦略的な発注計画の立案も可能となります。
経営判断や販売戦略の精度向上にも役立ちます。
システム化により、場所や時間を問わず受発注業務が可能となり、リモートワークにも対応できます。
24時間受注受付や注文処理ができるため、顧客対応力の強化にもつながります。
受発注システム導入は、目的の明確化・現状把握・システム選定・教育・本稼働まで段階的に進めることが成功のポイントです。
まず、現状の受発注業務にどんな課題があるかを担当者や現場からヒアリングし、課題をリストアップします。そのうえで、「受発注システム導入で何を達成したいのか(例:入力ミス削減、作業負荷の軽減、コスト削減など)」を明確にしましょう。
目的が曖昧なまま進めると、機能が合わない・現場で使われない・費用対効果が出ないといった失敗につながるため、導入目的は必ず明確にしておきます。
失敗しないためにもゴール設定や現場の声を反映し、システムの方向性を最初にしっかり決めましょう。
ステップ1で設定した目的をもとに、どの業務をどこまでシステム化するかを現在の業務フローに沿って整理します。このタイミングで、既存の会計システムや在庫システムなど外部システムとの連携要件も必ず確認しましょう。
自社の業務に必要な機能が揃っているか、将来の拡張性も含めてシステムを選定することが重要です。
システム化する範囲を決めたら、移行計画に基づいてマスタ情報の登録や設定を進め、設定後の動作検証を行います。
検証時には、実際の業務データを使い、操作性や連携機能、エラー検知などをしっかりチェックしましょう。この段階で現場担当者に操作してもらい、教育やマニュアル整備も進めておくと本稼働後の混乱を防げます。
検証段階で現場のフィードバックを取り入れることで、より実務に即した運用が可能になります。
検証が完了し、システムが想定通りに動作することを確認できたら本稼働となります。
取引先にも新システム利用の案内や説明を事前に行い、協力・同意を得ておくことがスムーズな切り替えのコツです。
また、導入効果を測定するため工数削減やコストカットなど数値目標を設定し、導入後も継続的に運用改善を行いましょう。
本稼働後も定期的な見直しや改善を行うことで、より高い効果を維持できます。
受発注システム導入でよくある失敗を防ぐには、以下の点に注意が必要です。
受発注システム導入後は、自社だけでなく取引先にも同じシステムを利用してもらうことがほとんどです。
事前に取引先へ導入の説明を行い、システムのメリットや操作方法、サポート体制なども伝え、同意・協力を得ておきましょう。
取引先の業務フローやシステム環境も考慮し、Web・EDIなど双方にとって最適な方式を選ぶことも大切です。
新システム導入で業務内容が大きく変わることも多いため、担当者の教育やマニュアルの整備、トライアル運用の実施が欠かせません。
操作に不安がある場合は、実際にデモやトライアル期間を設け、現場の声を反映しながら本稼働を迎えると安心です。
現場が使いやすいUIやサポート体制の充実も、システム選定時の重要なポイントです。
受発注システムは、会計・在庫・物流・基幹システムなど他システムと連携する場面が多いです。
システム導入前に、外部連携の方法や対応フォーマット、手動での補完作業の有無まで細かく確認しましょう。
既存システムとの連携実績や、トラブル時のサポート体制が整っているかも選定基準に加えましょう。
受発注システムの選定ポイントや連携事例は、以下の記事で詳しく解説しています。
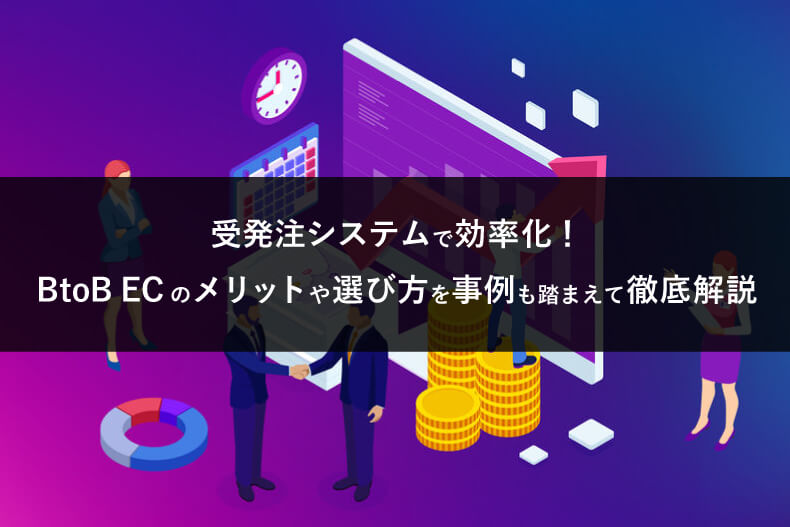
受発注システムを導入すれば、業務効率化・人的ミス削減・コスト削減・データの一元管理が実現できます。ただ、導入前に目的を明確化し、現場や取引先との合意や教育、外部システム連携などを丁寧に進めることが失敗しないポイントです。
自社の課題や成長戦略に合ったシステムを選び、将来の拡張や運用改善にも柔軟に対応できる体制を整えておきましょう。
受発注システムの導入やリニューアルでお悩みの際は、豊富な実績を持つecbeingまでお気軽にご相談ください。
